楽しく遺言書を作成したい方へ
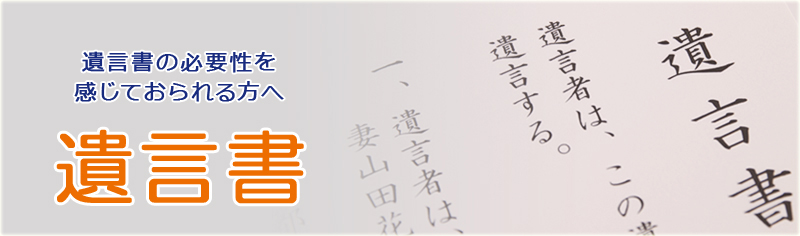
1. 遺言書を作ることは意外と楽しいのです。
『遺言書を作って欲しい。』と息子さんや奥さんが旦那さんにお願いすると旦那さんはどのようなご気分でしょうか?
普通は、『俺はまだ死なない。』、『俺を殺す気か!』、『俺に死んで欲しいんか!』なんて、心で思ったり、口に出してしまったりして、家族同士で喧嘩になったり、『縁起が悪い。』などと思ってダブ―となったりします。
遺言書で大切なことは、もちろん、法律上有効な遺言を作成すること、揉めないように遺留分に留意した遺言書を作成すること、できれば相続税の対策を行った遺言書がベターです。
しかし、私のお伝えしたいことは、遺言書を作成することで、残された人生がそう長くはないかもしれないことに気が付くことです。自分の死を意識することは、残された人生をいかに生きるかということにつながります。
『自分の人生が後24時間しかなければ、いったいどんなことをしますか?』とお尋ねすると皆さんは、家族と過ごすと言います。
『ご家族と過ごして、何をお伝えしたいですか?』とお尋ねすると皆さんは、奥さんや旦那さんへ『今まで長い間本当にありがとう。』と感謝の気持ちを伝えたり、『愛しています。来世も一緒にいたい。』と愛の気持ちを伝えたり、お子さんに対して、『一生懸命楽しく生きて欲しい。』とか、『家族を大切にして欲しい。』という言葉を掛けたいとおっしゃいます。
私は、45歳の時に第1子を授かりましたが、我が子を胸に抱いて、愛と感謝の気持ちでいっぱいでした。それと同時に、自分も愛され、感謝されながら生まれてきたのだと思いました。
人は、愛され、感謝されながら生を受け、周りの人に愛と感謝の気持ちを伝えながら死んで行ければ、人生は大成功ではないかと思いました。
私は、遺言書を作成することにより、ご自身の死を明確に意識することで、亡くなるまでの間に、周りの方々に愛と感謝の気持ちを思い出してほしいと思っています。
そして、遺言書で、愛と感謝の気持ちをご家族にお伝えし、亡くなった後でもご家族に格言を残して、亡くなった後もご家族の心の支えとなって頂きたいと考えています。
ご夫婦で、遺言を作ることで、お互いの大切さを再度思い出して、お互い仲の良い人生を送っていただければ嬉しいです。
子供さんに格言を残し、お子さんが人生で苦難に陥ったときに、支えていただければ私としてもうれしいです。
『遺言書を作成して、本当に良かった。』と泣かれるご夫婦が多いです。
遺言書を作ることは、縁起が悪いことなんてことはなく、大切なことに気が付き、その後の人生が充実し、意外と楽しいものなのです。
2. 遺言書作成の特に必要性が高いといえる場合
以下に当てはまる方は、相続発生後、遺産分割協において、紛争等が生じるリスクが非常に高いので、是非、遺言書の作成をご検討ください。以下に当てはまらない場合でも、可及的に紛争を予防するために、弁護士のアドバイスを受けつつ、遺言書を作成されることをお勧めいたします。
① 相続人が一人もいない場合
子供や妻、親、兄弟がいない場合は、法定相続人がおりません。そのような場合で、従妹など相続させたい人がいる場合には遺言書の作成を作成する必要があります。遺言書を作成せずに亡くなりますと、相続財産管理人を選任する手続を行って、従妹が特別縁故者として届け出て初めて財産を相続できることになります。この手続きによっても、4か月程度は処分行為ができませんので、予めお世話になっている方がいらっしゃる場合は、遺言書を書いてあげた方がいいでしょう。
② 内縁の配偶者がいらっしゃる場合
内縁の配偶者には相続権はありません。内縁の配偶者へ財産を残したいと考えられている場合は遺言書を作成して、遺贈しないと内縁の妻は何ももらえないことになります。被相続人所有の自宅で同居されているような場合、被相続人が亡くなられますと、内縁の妻が相続人から、自宅退去を要求されることもあります。遺言書の作成が必要不可欠なケースといえます。
③ 既に死亡した長男の嫁の世話になっている場合
長男とお嫁さんとの間に子供がいれば、その子供が相続することが可能であり、長男さんのお嫁さんも事実上、子供の相続により住居などを確保することができます。しかし、長男さんとお嫁さんとの間に子供がない場合は、長男さんの父母と養子縁組しない限り相続権はありません。遺言もなければ、相続人から、自宅建物から退去を要求されることもあり得ますので、遺言書の作成は必要不可欠です。
④ 夫婦間に子がなく、現在居住する不動産がほぼ唯一の財産である場合
夫が亡くなり、夫に直系尊属や兄弟姉妹がいる場合、妻と共同相続となます。妻が自宅建物に居住し続ける場合は、妻は他の相続人に代償金を支払わなくてはならなくなります。
⑤ 相続人資格者の内行方不明者がいる場合
相続が発生すると行方不明者のために相続財産管理人を選任する必要があり、その報酬の負担も被り、処理に長期間を要することとなります。
⑥ 家業を継ぐ長男に事業用財産を継がせたい場合
兄弟姉妹で事業用の財産を分割すると事業継続が難しくなりますし、遺産分割審判では家業従事者の寄与分はほとんど認められないので、事業継続のためには遺言書の作成が必要となります。
⑦ 先妻との間に子供がおり、現在、後妻がいる場合
先妻の子と後妻との話し合いは極めて困難となるケースが多いといえます。先妻の子を後妻が育てたというケースでも、後妻の他の子供がいる場合は、先妻の子供が不利に扱われる可能性もあります。ケースバイケースといえますが、遺言書による事前対策が必要なケースといえます。
⑧ 離婚状態にある別居中の配偶者がいる場合
子供がいればもめないことも多いですが、子供がいない場合は、両親及び兄弟姉妹と配偶者が対立しやすいことから、遺言書の作成が必要なケースといえます。


